
「クリエイティブ思考×社会課題~横浜を豊かにする種を考える~」開催レポート
2025年2月27日(木)、「クリエイティブ思考×社会課題~横浜を豊かにする種を考える~」を開催しました。
開催概要
【日 時】2025年2月27日(木)14:00~16:30
【場 所】横浜市市民協働推進センター スペースAB
【登壇者】永田 宏和(ながた ひろかず) 氏
・デザイン・クリエイティブセンター神戸【KIITO】 センター長
・株式会社iop都市文化創造研究所 代表取締役
・NPO法人プラス・アーツ 理事長
今回のセミナーでは、デザイン都市神戸の拠点施設であるデザイン・クリエイティブセンター神戸(KIITO*/キイト)の永田宏和さんをお招きし、クリエイティブ思考による社会課題解決の事例から、企画立案に必要な要素やプロセス、また、それを社会に広げるために必要なことを学びました。
その後のトークセッションでは、これまで横浜で行われてきた市民活動を振り返り、これからの横浜の発展に必要なことを語り合いました。
*KIITOとは、「+クリエイティブ」をキーワードに、デザインの視点により、さまざまな人々の交流から生まれるアイデアや工夫を採り入れ、身の周りの社会的な問題を解決していくことを実践しているセンターです。

永田さんによる講演「クリエイティブ思考×社会課題」
最初に、クリエイティブ思考をともなった社会課題へのアプローチについて、永田さんよりご講演いただきました。
まず、地域や社会で活動をつくる時の心構えとして大切なことの一つは、「俯瞰する」ことであるというお話から始まりました。「俯瞰」には、「地縁関係の俯瞰」と「時間軸の俯瞰」の2つがあり、一つ目の「地縁関係の俯瞰」とは、なにかプログラムを作る際に、支援対象などそのターゲットにフォーカスし過ぎず、少し引いて見渡すことで地域や周辺にいる様々な関係者の存在に気付くことだそうです。そして二つ目の「時間軸の俯瞰」とは、一般的になにかプログラムを作る時には、そのプログラムを実施することがゴールであると考えられがちですが、プログラムの実施はあくまでプロセスであることを前提に、その後の展開を意識した前段階をつくることであるという説明がされました。
また、高齢者が増え、人口が減っている現在において、地域の人たちがお互い仲良く、生き生き暮らす元気なまちになることを「地域活性化」ではなく、「地域豊穣化」と呼んでいるそうです。そして地域豊穣化を実現するための重要な役割として、「風の人」「水の人」「土の人」が存在します。
「風の人」:その土地に「種」を運ぶ、刺激を与える存在。
「水の人」:その土地に寄り添い、種に水をやり続ける存在。中間支援的存在。
「土の人」:そこに居続ける存在。しっかり根を張り、活動し続ける存在。
出典:NPO法人プラス・アーツ
しかし、超高齢化社会や人口減少などの影響もあり地域コミュニティは崩壊気味で、「土」が枯れていく一方であるため、「『種(イベントや活動)』を品種改良し、『強い種』にしていくことが求められている」と述べる永田さん。そのためには、地域に「風の人」の存在が必要不可欠だと言います。

ではどのように「風の人」がいい「種」を生み出し、地域へ運ぶことができるのでしょうか。ここでは、「不完全プランニング」と「+クリエイティブ」という手法の2つの考え方をご紹介いただきました。
「不完全プランニング」とは、活動のリーダーがプログラムのすべてをあらかじめ決め過ぎないことを指します。不完全であることで、他の人たちが関わる余地が生まれ、一緒に活動を作り上げることができます。次第に活動がみんなのものになり、地域に定着しやすくなるという効果があります。
そして「+クリエイティブ」という手法は、プログラムやイベントを魅力化することを指します。ただ企画を実施するだけでは、関係者や周囲の人たちは面白みを感じることができず離れていってしまいますが、「楽しさや美しさ、感動、非日常、ワクワク、かっこよさ、親が子に経験させたいこと」などの要素を入れることで、プログラムやイベントが魅力的になり、人を惹きつける力になります。
永田さんからは、「クリエイティブとは、新しい何かを創り出すことであり、そこには既存のものをぶち壊すという意味も含まれる。つまり、すべてゼロから新しく何かを創り出すことだけではなく、今ある何かを作り直したり焼き直したりすることも、クリエイティブである」という考えが共有されました。

永田さんがセンター長を務めるKIITOは、「みんながクリエイティブになる。そんな時代の中心になる。」をスローガンに活動しています。デザインやアートに加え、既成概念にとらわれないアイデアや工夫を採り入れ、身の回りの社会課題を解決する「+クリエイティブ」という手法をベースに、こどもの教育や高齢社会、観光、まちづくりなどにおいて様々な種(神戸モデル)が生まれ、広がっています。
KIITOのHP(外部リンク)
横浜の種
では横浜にはどのような種があるのでしょうか。
初めに、横浜市市民協働推進センター副センター長(当時)の韓より、横浜にある「種」の事例が4つ紹介されました。

①一緒にコーヒーを楽しみながら地域活性化
本格的なコーヒーを淹れることができる珈琲愛好者のボランティアが、バザールなど地域のイベントでコーヒーをきっかけに地域の交流を生み出し、様々な地域貢献を展開している。
②犬と地域貢献「わんわんパトロール」
愛犬と散歩をしながらパトロール活動をすることで、安全安心なまちづくりに貢献している。地域によっては腕章やバンダナなどを配ったり、SNSで投稿し拡散したりしている。今後は、地域の見守りを担っているという観点から、各区の地区社会福祉協議会や地域ケアプラザなどと繋がって、活動をより広げていこうとしている段階である。
③横浜が大好きな市民によるシティガイドボランティア
地域の資源や歴史が大好きな人たちがその魅力を紹介する活動である。参加者と一緒にオリジナルのコースを歩き、市民の視点から、横浜の歴史的な要素や新しい情報を話の中に交えながら、地域をガイドする。
④気軽に立ち寄る場、住み開きカフェ
常設のカフェではなく、自宅の一部を開放し地域の人たちが集まる場を提供することで、コミュニティづくりや安全安心なまちづくりに貢献する。緑区社会福祉協議会がそのブランディングとして旗を配布している。

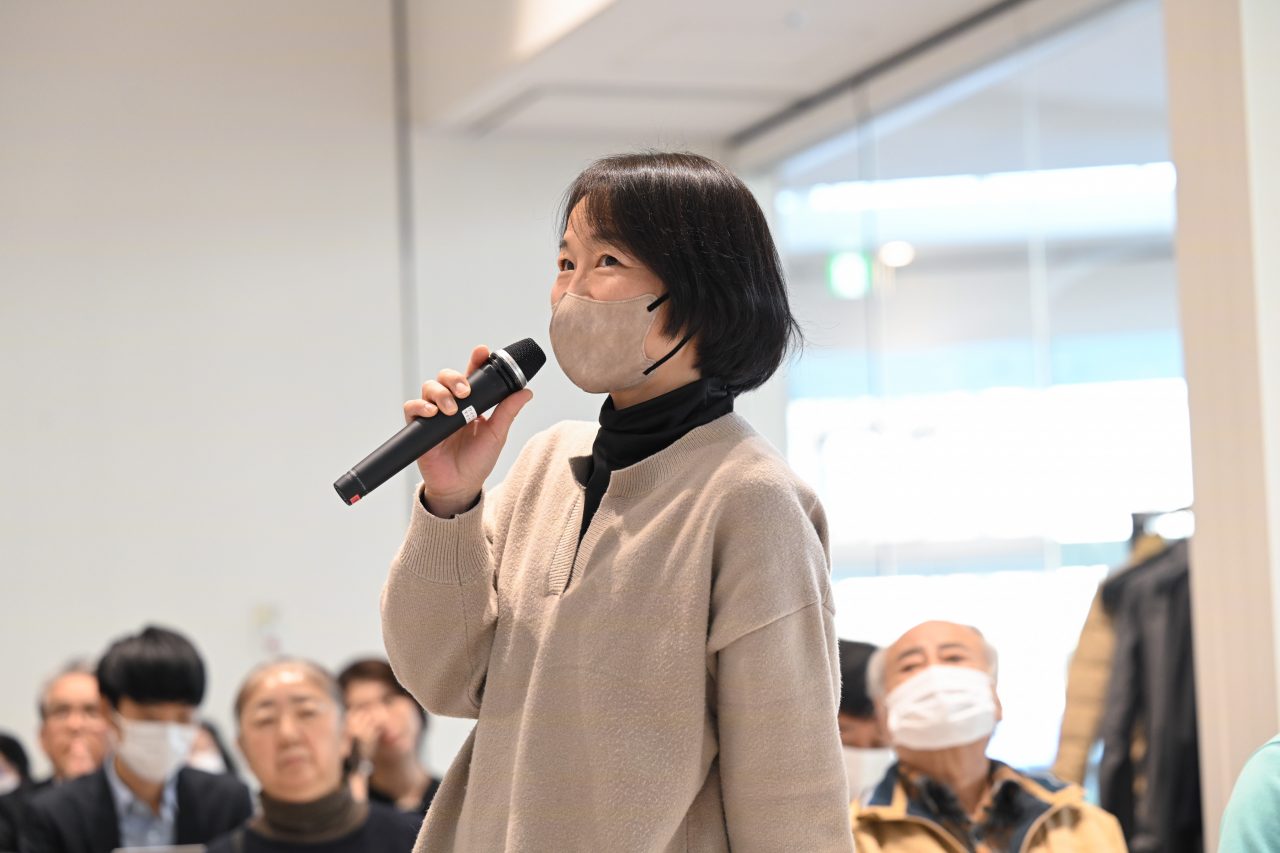
トークセッション「横浜を豊かにする種を考える」
その後、これらの事例を踏まえて、「横浜を豊かにする種を考える」というテーマで、永田さん、伊吾田センター長(当時)、韓副センター長(当時)の3人でトークセッションが繰り広げられ、様々なヒントが挙げられました。

クリエイティブ思考による社会課題へのアプローチを進めるにあたって、まずは「やってみる」を大事にしていると話す永田さん。やってみることで、思いもしなかったところにつながる可能性があったり、新しい仲間ができたりしていくことがその良さであると言います。また、やってみて上手くいかなくても失敗ではなく、課題の発見の機会と捉え、どう改善していけるかを考えるそうです。


「やってみる」の良さを大事にしつつも、「リサーチ」の重要性についても指摘されていました。リサーチと言っても、「リサーチしなくては」というよりは、「日常」がリサーチであると語る永田さん。アンテナを普段から張り、何でも興味関心を持つ―そのように日常的なリサーチを繰り返していると、勘も良くなっていくそうです。ただ、現場で実際に体験したこととネットに載っている情報はまったく異なり、失敗体験が書かれていないなど、リサーチをする際にネットの情報に頼りすぎると、的外れなことを企画してしまう可能性もあります。
一般的に、世間では失敗を良しとしなかったり、失敗することを人は恐れたりしていますが、「やってみる」ことが「リサーチ」にもなります。
さらに、永田さんよりお話があった「不完全プランニング」に関連して、行政との関わりとトライアルの難しさやその可能性について、議論が広がりました。
行政とともに仕事を進めている組織の場合、不完全プランニングという形でチャレンジしてくことが、運営や資金という側面からより難しい部分がありますが、「そのような中で不完全プランニングに対する前向きな雰囲気を醸成するためにはどうすれば良いか」という投げかけに対して、「行政職員も仲間であるということを認識し、思いを持った同志のコミュニティを作っていくことが良いのでは」という回答がありました。

永田さんによると、今となっては神戸の中でKIITOや永田さんの存在が確立されていますが、活動を始めた当時は様々な意見があったそうです。しかし、最初のモデルを作った時に行政の中にいる面白い人たちが集まってきたと振り返る永田さん。行政の中に熱意や想いを持った人はいるため、「部局」ではなく「人」がキーとなって、協力者や応援者が増えていった経験から、その先に成果を上げていくことで、それ以外の人たちにも理解していってもらうという段階が提示されました。
今回の講演には、NPO法人等の市民活動団体や企業、市内の中間支援を担う職員の方々に加え、多くの行政職員の方の参加がありました。
事前のアンケートでは、
「クリエイティブな視点で課題解決、さらにデザインするというのはどういうことなのか知りたい」
「クリエイティブ思考による社会課題解決の事例から、企画立案に必要な要素やプロセス、また、それを社会に広げるために必要なことを学びたい」
など、活動や業務を行うにあたり課題感を持っていたり、永田さんやKIITOの話に高い関心がある参加者が多くいました。



永田さんの講演やトークセッションを経て、
「地域の課題解決には、楽しさ面白さを真ん中にしてみること、類似事例ではなく先進事例を探すこと、リサーチの大切さ、俯瞰することなどを学べた」
「活動するにあたり、これまでに無かった視点を得ることができた」
「とりあえず思いついた事をまずはやってみている中で失敗も多いので不安だったが、これからも『まず、やってみる!』で活動していく自信がついた」
「イベントは通過点であって、その後にどうつなげるかのお話や水・風・土の話を企画立案時に意識しないといけないと感じた」
「社会課題を解決する仕掛けをどのようなプロセス、思考で考えていくのか、ポイントがわかりやすく大変参考になった」
「具体例を交えて非常に内容の濃い講座だった。自身の携わっている業務も改めて見直してみたいと強く感じた」
「地域支援に対して視野が広がった。普段は心のどこかで諦めていることもあったような気がするが、こんなことやれたらいいな、がたくさん思い浮かんだ」
など、活気のある、熱のこもった感想を多くいただきました。
終了後も、永田さんの前には質問のために長蛇の列ができました。


改めて、永田さんの活動やKIITOの事例に対する関心の高さがうかがえました。
また参加者同士でも名刺交換が行われるなど、所属を超えた交流も深まりました。



おわりに
今回は、「クリエイティブ思考×社会課題」というテーマで、クリエイティブ思考による社会課題解決の事例から、企画立案に必要な要素やプロセス、またそれを社会に広げるために必要なことを学びました。さらに、横浜で行われてきた市民活動を振り返り、これからの発展に必要なことを語り合いました。
クリエイティブ思考と同時に、地域や社会課題の解決には、多様な主体がそれぞれの強みを活かして協働・連携することも重要です。市民協働を推進する機能を担う当センターとしても、横浜市をより良くしていくために、熱い想いや課題感を抱えている市民および行政職員の皆さまとの繋がりを大切にしたいと感じています。
今後も皆さまに役立つイベントやセミナーを実施していきます。当センターが主催するセミナーやイベントの情報は、随時HPやSNS、メールマガジンに掲載しております。今後も皆さまのご参加をお待ちしております。
〇メールマガジンのご案内〇
センターからのお知らせや各種イベント情報、助成金情報などを定期的にお届けしています。ぜひご登録ください!
メールマガジン(Civic Times)のご案内

