
協働ステップアップセミナー Vol.2「『地域を知る・好きになる』から始まる地域づくりと担い手育成」開催レポート
2025年9月5日(金)、協働ステップアップセミナー Vol.2「『地域を知る・好きになる』から始まる地域づくりと担い手育成」を開催しました。
皆さんは、地域を知る・好きになることが、地域づくりやその担い手育成につながるということを考えたことはありますか?
近年、地域の担い手不足が問題視されていますが、地域を知ること、そして好きになるということが、この課題にどう良いインパクトを与えうるのか、そしてその仕掛けづくりをどのように行ってきたのかを、認定NPO法人森ノオト理事長の北原まどかさんにお話しいただきました。その後のグループトークでは、参加者同士で気づきや学び、今後の活動や仕事に活かしていきたいことなどを共有し合いました。

開催概要
【日時】2025年9月5日(金)15:00~17:00
【場所】横浜市市民協働推進センター スペースAB
【講師】北原まどか氏(認定NPO法人森ノオト 理事長)

北原さんが理事長を務める認定NPO法人森ノオトは、「地域や自然と調和した社会と、その担い手を育てる」ことをビジョンに掲げ、「暮らしの足元から地域を編集し、一歩を踏み出すきっかけをつくる」こと―まさに今回のセミナーの趣旨や問いかけを団体のミッションとしています。ローカルメディア「森ノオト」の運営を軸に、
・ローカルメディアデザイン事業部:各地の市民ライターの育成や地域活動団体の発信力UP支援など
・コミュニティデザイン事業部:青葉区を拠点にした地域協働の実践、子育て支援など
・ファクトリー事業部:寄付布循環事業「めぐる布市」の運営など
が展開されています。
北原さんご自身は、母親が有機野菜の共同購入をしていたことから、環境、福祉などの分野に興味を持たれ、大学・地域新聞発行・フリーランス時代の様々な出会いや出来事がきっかけとなり、森ノオトとしての活動につながっているそうです。
“Think Globally, Act Locally”をモットーに、特に”Act”の部分をどうつくるかを2009年の創刊当初から考えていたと振り返る北原さん。当時の構想を書き下ろしたメモも共有していただきました。
誰かの一歩を踏み出すきっかけをつくる―市民ライター養成講座という切り口
住民が地域に参画する一歩を踏み出すきっかけづくりの一つとして、市民ライター養成講座があります。これは森ノオトが毎年1~3月にかけて全6回開講しています。
森ノオトの活動を続けていく中で頻繁に来てくれる人―好奇心が高く、「何かやりたい」という思いを持った人たち―に出会ったことで、最初は北原さんご自身がヘッドハンティング式でライターを集めていたそうですが、その後、ライター仲間向けに体系化した編集ノウハウを伝えていこうと、ライター養成講座が展開されていきます。
ライター養成講座を切り口に、「子と二人で過ごす時間が多いが、地域に関わりたい」「これまでのキャリアを活かしたい」という子育て世代の背中を後押しするきっかけとなっているそうです。また、子どもの居場所支援をしている団体を取材したことで、相手の活動の理念や想いを深く知り、ボランティアとして関わり始め、最終的にスタッフとなったライターや、取材がきっかけで取材先に就職したライターもいるのだとか。まさに地域の出来事や活動を知ることが、地域の一員として活動することに密接につながっているということがわかる事例です。

そして森ノオト自体がライター一人ひとりのあり方を丸ごと受け入れることを大事にしていると話す北原さん。ライター自身の問題意識や伝えたいこと、なにより「挑戦したい」という想いを形にできるよう応援できる体制づくりがされています。今では青葉区に限らず、他区や他都市からもライター養成講座の依頼が広がり、各地でライターのコミュニティが生まれています。
記事作成は協働作業
一つの記事を作り発信するには、編集者とライター、取材相手、読者など多くの主体が関わっています。ここで北原さんは、「記事づくりに関わる全ての人が『対等』であること」を大事にしていると言います。「取材させていただく」「取材される」という関係性ではなく、「まちの魅力を伝える」という共通の目的を持ち、一緒にまちをつくっていく仲間として関わることが重要だそうです。地域づくりは「やってあげる人」「やってもらう人」という構造では成り立ちません。地域の一員として対等な仲間がいることで、その地域への愛着がますます強くなっていきます。
「私」(=主観)を尊重する
一般的に記事の作成や情報発信において求められるのは、「客観性」ではないでしょうか。しかし森ノオトでは、「私」(=主観)を尊重した取材や記事作成を行っているそうです。これは、地域に暮らす住民として語る当事者性が生まれ、自分の関心や悩みを開示することで社会的な関心・悩みとして広げることができるという強みになると説明がありました。このように、個人が落とした一滴が波紋となり、社会に良い揺らぎを呼び起こせているかということを考えられています。
ただ、主観に溢れた想いを語る内容を記事として発信しているわけではありません。そこに事実の有無や具体的な数字、科学的な根拠などの客観的な視点から、「読者に伝わるか」「ライターの独りよがりになっていないか」を編集者が確認し、記事の質を担保しているそうです。
一方で、行政職員は客観的であることに非常に長けていますが、特に地域の住民や活動に近い立場で仕事をしている人は、行政職員という立場で線を引いて地域と関わるのではなく、地域の一員として「もっとそれぞれのキャラクターを出していき、『この人に聞けば何かわかる』という人間関係を区民の方とつくっていけたら良いのでは」という投げかけもありました。

コスパでは計れない、未来への贈り物
近年ではSNSの発達により、手軽に短時間で情報を掲載できるようになりましたが、森ノオトでは1本の記事を発信するまでに2~3カ月かかるそうです。それに対して、外部の方から「『コスパ(コストパフォーマンス)』が悪いのでは」という声もあったそうですが、「社会に意味のあるもの、良質な情報を届けるにはそれなりの時間がかかる」と北原さん。また「よい地域情報は未来への贈り物」でもあると言います。
持続可能な地域や社会につながるか、誰かの心を温めたり、背中を押したり、一歩を踏み出したりすることにつながるかなど、情報を受け取った読者のポジティブな行動変容をイメージして、多様な主体が意見を交わしながら記事をつくっているそうです。このように幸せな地域情報が地域にあふれることで、幸せな地域をつくることにつながるのではないかと考え、これを「ポジティブ・フィルターバブル」と表現されていました。

メディア自身がまちづくりの軌跡をたどるアーカイブに
森ノオトは、自治会や公園愛護会、福祉施設、商店会、企業、学校、行政など地域に関わる非常に多様な主体と連携・協働をしています。協働のキーワードごとに取材記事がたまっていき、まちづくり情報がストックされている状態です。北原さんはそれを「地域情報のアーカイブが地域そのものに変化していく」と話します。
また、特に地域を良くしたり社会課題を解決したりするには、その分野に長けたNPOが行政と協働していくことが大事であるとの言葉がありました。NPOが記事作成や情報発信をする過程には、地域に暮らす人々の生の声を聞く機会が多くあります。つまり、NPOは情報発信をするなかでメディア機能を活用して、地域や市民の声・ニーズを行政にも伝えることができ、行政だけでは拾うことが難しい現場のニーズや声が、その地域のまちづくりにつながっていけば、NPOがまちづくりの担い手となることができる、と言えます。
その後のグループトークでは、北原さんのお話を踏まえて、学んだことや印象に残ったこと、今後実践していきたいことなどをグループ内で話し合いました。

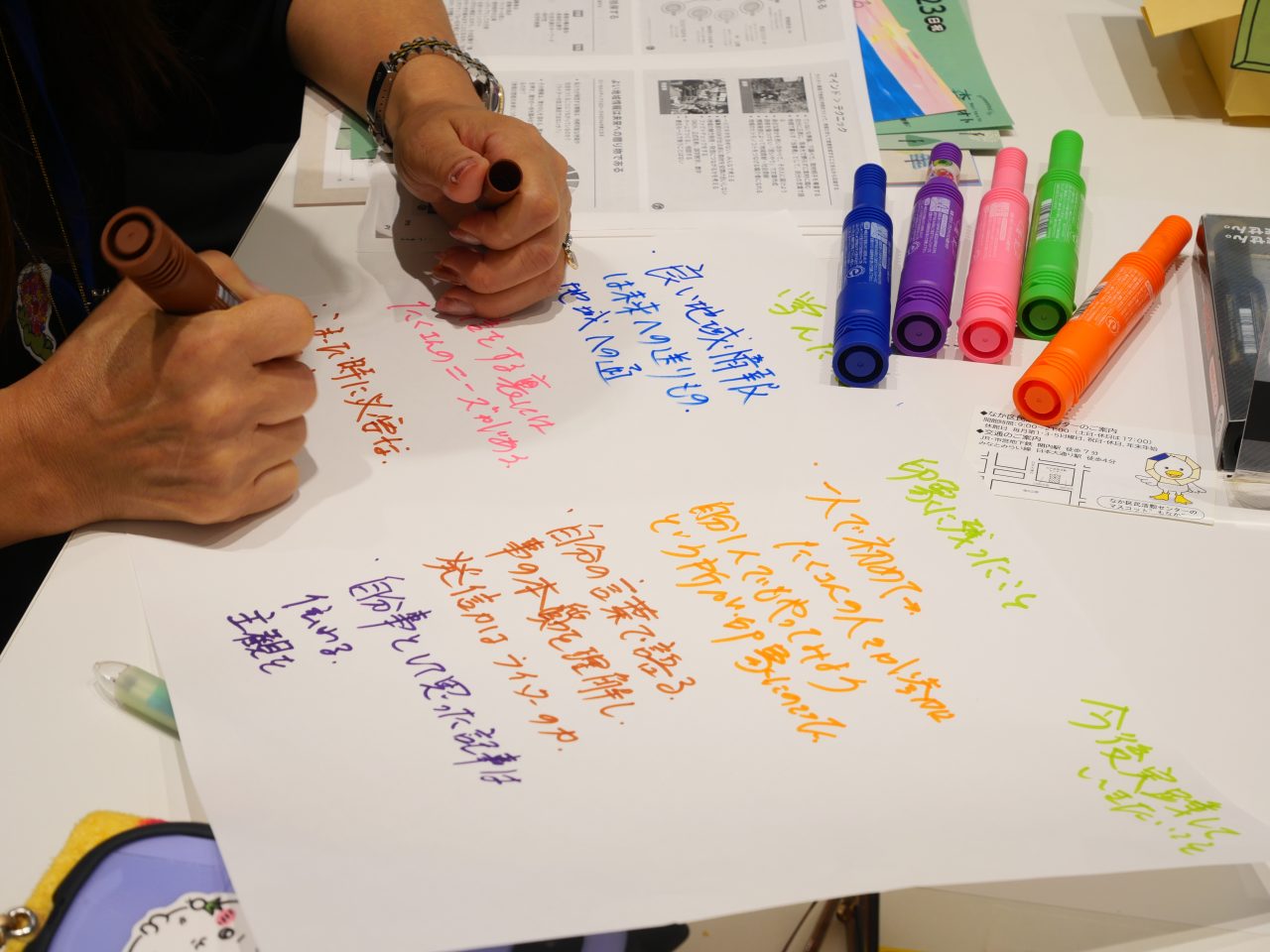

・「編集のプロセスが丁寧であることが、まちづくりにも通ずるということを知ることができた。まちづくりはコスパを求めるものではない」
・「行政はペーパーレス化を推進しているが、紙媒体の情報の重要性を認識できた」
・「発信者は地域のニーズを知っている人である」
・「“何か挑戦したい”“地域と関わりたい”という想いを持った人を継続してサポートすることのハードルを感じた。行政としてどこまでできるか考えていきたい」
・「地域の情報が散らばっているものをつなげて見える化していきたい」
という気づきやこれから取り組んでいきたいことが共有されました。
その後の質疑応答では、「子育てに忙殺されている層に情報を届け、参加を促すにはどうしたらよいか」という質問が挙がりました。それに対し、「森ノオトを立ち上げて7、8年目あたりは子育て世代に知られていなかった」と振り返る北原さん。ターゲット層に福祉の情報をどう届けるか考えたときに、「情報を届けたい相手はどこに行って何を見るだろうか」という視点で「こんにちは赤ちゃん訪問」を活用することや母子手帳と一緒に携行する小冊子を構想したそうです。また「ウェルカムあおば子育てツアー」と題して、1歳になる前の赤ちゃんを育てる子育て世代を対象とした街歩きツアーを青葉区に提案して5年ほど実施したそうで、参加者が地域を知ったり仲間とつながったりする機会にもなりました。
このように、子育て世代に情報を届けるならどこにどう出向くべきか、子育て世代につながっている行政の所管はどこなのかを探っていき、そしてその所管ができていない企画をつくっていくということをした結果、森ノオトの認知が広がっていったそうです。
おわりに
北原さんのお話を聴いて、「北原さんや森ノオトは時間をかけて高度なことをされている」と感じた方もいらっしゃるかもしれません。しかし、最後に北原さんが「自分自身の経験を言葉にして誰かに伝えることは、誰にでもできるはず。それが未来へのギフトにつながる」とおっしゃっていたのが印象的でした。
「地域と関わりたい」「何かしたい」という想いを応援する人や団体の存在がある。地域に暮らす一人の当事者として地域を取材する。その過程で地域活動に参画したり、生の声やニーズに触れたりする。記事作成を通して、「私」の経験や悩みを社会化する。社会化したことで、また誰かの一歩を踏み出すきっかけとなる。―このような循環を生み出し支えていくことが、持続的な地域づくりや地域に参画する人を増やすことにつながるということを、参加者の皆さまそれぞれの立場で改めて考える貴重な機会となっていればと思います。

今後も皆さまに役立つイベントやセミナーを実施していきます。当センターが主催するセミナーやイベントの情報は、随時HPやSNS、メールマガジンに掲載しております。今後も皆さまのご参加をお待ちしております。
〇メールマガジンのご案内〇
センターからのお知らせや各種イベント情報、助成金情報などを定期的にお届けしています。ぜひご登録ください!
メールマガジン(Civic Times)のご案内

