
1.はじめに──見過ごされがちな「きょうだい児」のための保育
横浜市内にある地域療育センターは、障がいのある0歳から小学校期までの子どもの発達を支援する施設です。療育の現場では、長年にわたりある課題が指摘されてきました。それは、障がいのある子どもの兄弟姉妹、いわゆる「きょうだい児」の居場所が十分に確保されていないという問題です。
障がい児の療育プログラムには保護者の付き添いが必要なため、その間、きょうだい児は別の保育施設に預けられます。しかし、障がい児をケアしながら、きょうだい児の預け先を探し、施設から離れた場所まで送迎する手間は、保護者にとって大きな負担になります。全てのきょうだい児に安心して過ごせる場所が用意されているとはいいがたく、現場ではその必要性が常に意識されていました。
この課題を改善するため、横浜市都筑区の「NPO法人のはらネットワーク」が、2019年度に「協働事業の提案支援モデル事業」で立ち上がった任意団体「ちょこっと子育てレスキュー隊(以下ちょこレス)」の取組の中できょうだい児保育を開始。2021年度には活動を発展させる形で「市民協働提案事業」に採択され、都筑区の横浜市北部地域療育センター内での預かり保育が実現しました。さらにこの取組が広く認められ、2024年度からは地域療育センターの予算内に組み込まれる形で事業を継続中です。同時期から、従来の北部地域療育センターに加え、青葉区の地域療育センターあおば、保土ケ谷区の横浜市西部地域療育センター、南区の横浜市中部地域療育センターの計4カ所できょうだい児保育が行われています。
横浜市市民協働推進センターでは、新たな公民連携の発信・対話の場をつくるイベント「ヨコラボ2023」で、ちょこレスによる「きょうだい児の地域での支援」の取組を市民協働の先進的な事例として取り上げました。今回はイベントでは伝えきれなかった事業の全体像、さらに「きょうだい児保育」の取組が横浜市へ展開されていく過程を深く掘り下げるためにインタビューを実施。お話しを伺ったのは、以下の4名の方々です。
・燕昇司知里さん NPO法人のはらネットワーク 保育士
・木村博子さん NPO法人りんぐりんく 理事長・横浜市主任児童委員代表
・髙橋洋子さん 認定NPO法人さくらんぼ 理事長
・中西美紗子さん 認定NPO法人さくらんぼ 事務局長
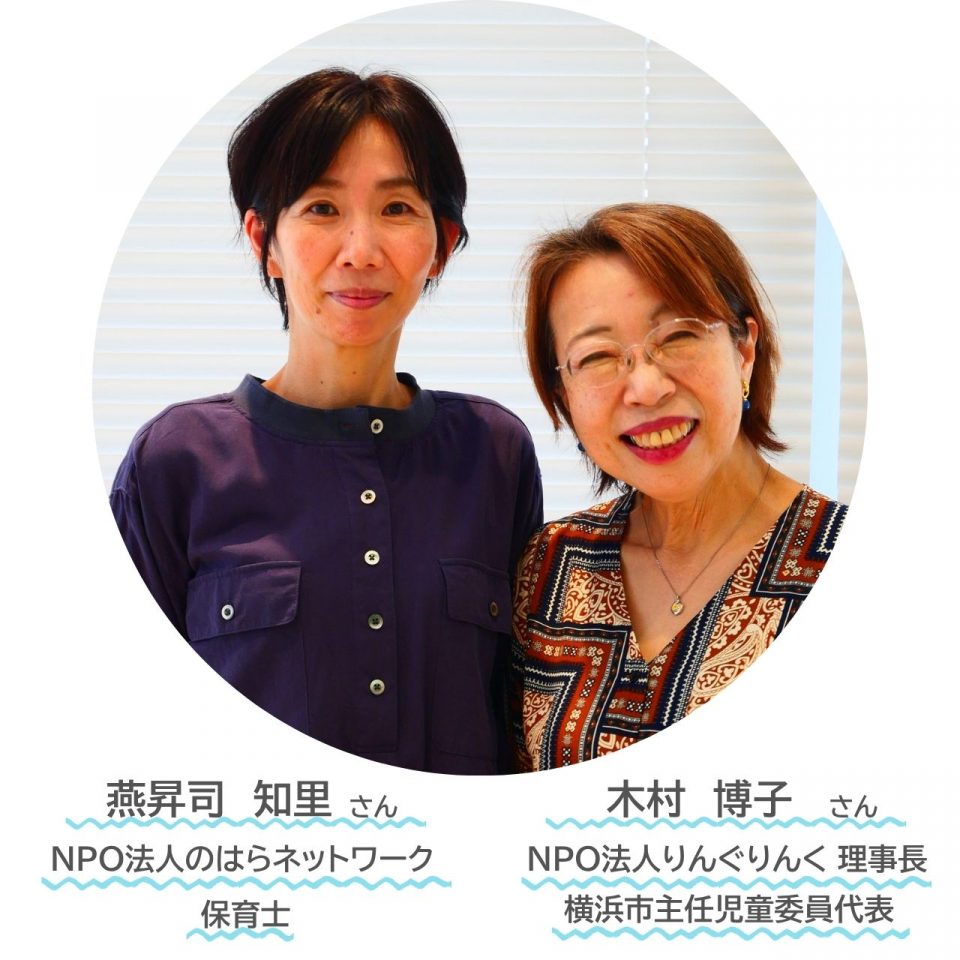


のはらネットワークは、北部地域療育センターで「ちょこぽん」、地域療育センターあおばで「たけのこ」というきょうだい児保育施設を運営しています。西部地域療育センターのきょうだい児保育施設「うさぎるーむ」は、「認定NPO法人さくらんぼ」が運営を担当。今回はお話を伺っていませんが、中部地域療育センターのきょうだい児保育施設「まるっと」では、「NPO法人さくらザウルス」が保育に取り組んでいます。
事業の始まりから現在までの変化を時系列にたどり、協働の魅力、保育を通じた家族支援の方法、地域への広がりなどを深く掘り下げました。市民協働のためのヒントをここから探っていきましょう。
2.地域を巻き込みながら始まった、きょうだい児保育
きょうだい児に注目した保育事業は、どのようにスタートしたのでしょうか。北部地域療育センターでは、もともと保護者がボランティアできょうだい児を一時的に預かっていました。一方、のはらネットワークの乳幼児一時預かり事業内ではきょうだい児の優先枠を設け、北部地域療育センターから利用者へ紹介されることもあったそうです。きょうだい児保育に対する重要性は以前から認識されていましたが、十分な支援体制が整っていたわけではありませんでした。
転機となったのは、ちょこレスの立ち上げです。地域の子育ての困りごとを協力して解決できるようなプラットフォームをつくるため、のはらネットワークが中心となり、りんぐりんくをはじめとする支援団体と連携しながら活動を開始しました。活動の柱の一つに掲げられたのが、支援の手が十分に届いていなかったきょうだい児を対象とする保育の実施です。
当初は、団体の意義やきょうだい児保育の必要性を理解してもらうことが難しい場面も多かったそうです。「それでも、とにかく地域を巻き込みながら、自分たちのビジョンを共有していきました」と木村さんは語ります。地域団体、児童家庭支援センター、社会福祉協議会などに協議会への参加を呼びかけ、さらに民生委員や自治会とも連携を進めました。こうした方々と行政機関へ何度も足を運び、少しずつ信頼関係を築いていったといいます。

2018年度には行政機関や支援団体などとともに事業内容のブラッシュアップを重ね、翌2019年度に「ちょこっと子育てレスキュー隊事業」が協働事業の提案支援モデル事業に採択されます。これを機に、きょうだい児保育事業がスタートすることになりました。認可外保育施設として一時預かり保育を実施するにあたり、保育士としての経験が豊富な燕昇司さんが事業の中心を担っていきます。
3.地域療育センター内での保育へ
3-1. “協働”が持つ力の発揮
この時期の保育は、北部地域療育センターから車で1・2分ほどの場所にある都筑区平台の自治会館で行われました。わずかな距離とはいえ、その移動が保護者にとっては負担になることに変わりはありません。加えて、ボランティアが担っていた北部地域療育センター内でのきょうだい児の一時預かりは、コロナウイルスの感染拡大が影響し、活動の停止を余儀なくされます。
この状況下で、ちょこレスは施設内で預かり保育を実施するための準備を進めました。その過程について、燕昇司さんは「まさに“協働”の力が発揮されていました」と明言します。
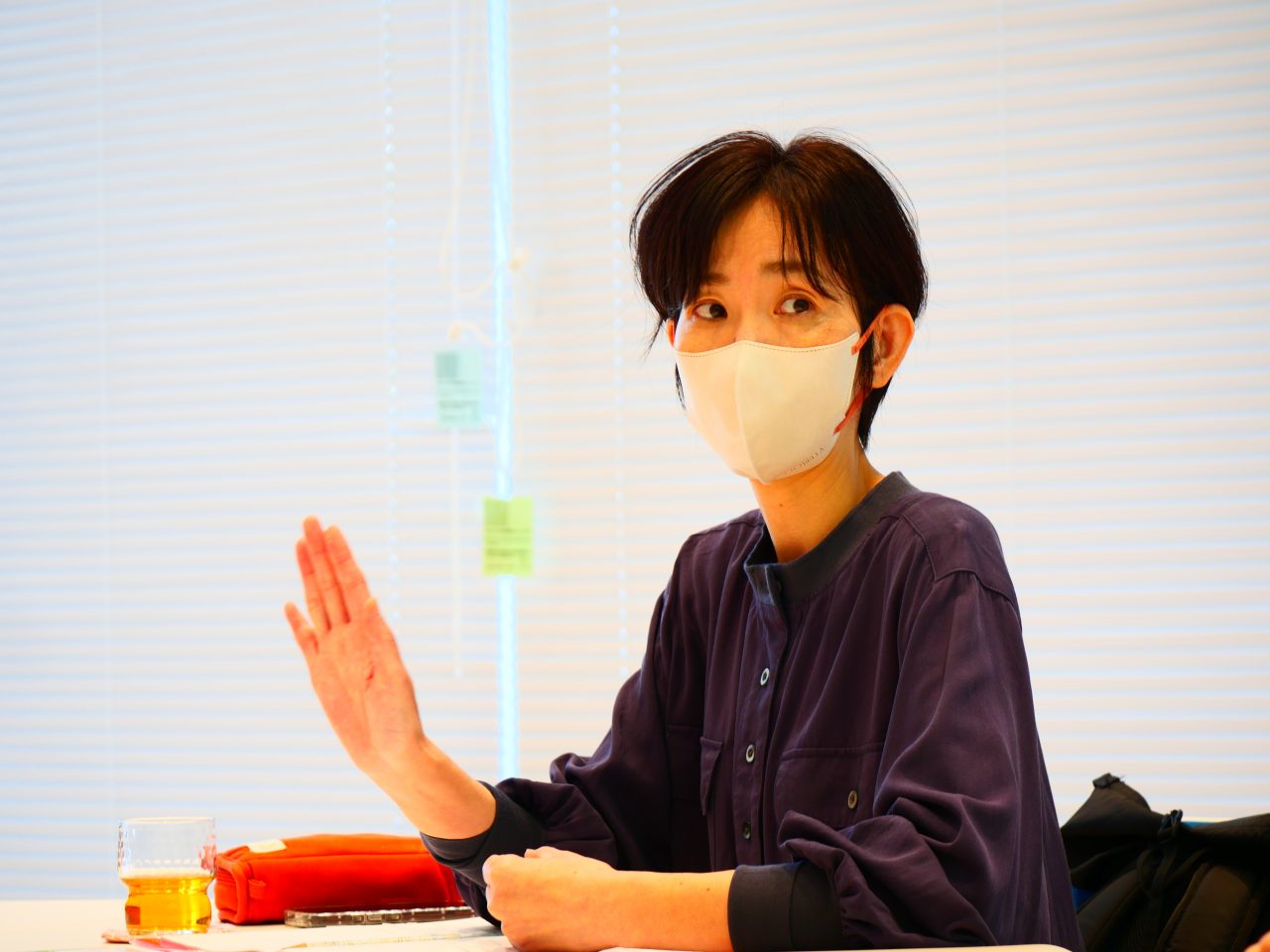
任意団体が地域療育センター内で保育を行うには、複数の行政部署との調整が必要でした。建物の管轄は横浜市であり、障がい児の療育は地域療育センターとこども青少年局こども福祉保健部障害児福祉保健課、きょうだい児の保育は都筑区こども家庭支援課がそれぞれ担当しています。さらに市民局市民協働推進課とも協力しながら、各部署が調整を重ねていきました。
その結果、2021年度から北部地域療育センター内でのきょうだい児保育が、市民協働提案事業として実現されます。当初は、毎週金曜日のみの実施でしたが、週3日通所する家族からは、「金曜日の通所が本当に楽になった」という喜びの声が寄せられたといいます。

(画像提供:のはらネットワーク)

(画像提供:のはらネットワーク)
3-2. 保育から家族を支え、地域へつなげる
北部地域療育センター内での保育が始まって間もなく、この取組自体が障がい児を育てる家族への支援へ強く結びついていることを、燕昇司さんを含む支援側の人々が改めて実感したそうです。保護者へのアンケートでは、「精神的な安心感を得られた」という回答が多く集まりました。北部地域療育センターからも「療育を休むことが減り、保護者や障がい児が療育に専念できるようになった」、「保護者の精神状態が非常に安定した」などの反応がありました。
さらに、燕昇司さんは「家族を孤立から防ぐために、家族を地域の様々な場所とつなげること」を実践していたといいます。のはらネットワークはもちろん他の地域団体の一時預かり保育サービスや、都筑区子育て支援センター「Popola(ポポラ)」のイベントへも保護者をつなげていきました。
障がい児の保護者は「地域の施設やサポートは障がい児向けではないため、家族が気軽に利用できない」と思い込みがちです。そこで保育士やサポーターは、紹介先へ事前に連絡を入れるなど、保護者が安心して利用できるよう配慮しました。「家族と地域をスムーズにつなぐことができるのは、ちょこレスのネットワークがあるからこそです」と燕昇司さんは自信を持って話します。
3-3. サポーター制度で障がいに対する理解を深める
事業を円滑に進めるため、保育に携わるボランティアサポーターの募集へ力を注いできました。子育ての悩みを共有する「だれでも勉強会」を定期的に開催し、きょうだい児保育へ興味を持った人に協力を仰ぎました。一時預かり保育を過去に利用した保護者が、サポートする側として活躍できる支援の循環を生み出すことも目指しました。これらの努力が功を奏し、現在でも多くのサポーターが安定的かつ継続的に関わっています。

(画像提供:のはらネットワーク)
保育の現場に参加することで、サポーターは障がい児やきょうだい児の現状、家族の苦悩を目の当たりにします。その経験により、障がい者への理解がリアルな形で深まっていくといいます。これは、障がいに対する理解不足から生まれる偏見や差別を減らすことに直結します。
燕昇司さんはサポーターに、「地域で困っていそうな障がい児と家族を見かけたら少し注意しながら見守り、助けが必要であれば声をかけてください」と伝えています。保育を通じて、地域の意識やまなざしが少しずつ変わり、小さな優しい行動が積み重ねられていく。細やかな変化を地域の中に創出できている点も、この取組の大きな成果といえるでしょう。
保育に興味はありつつも関わる機会がなかった人や、子育てに専念して働く機会がなかった人など、サポーター自体も多様な背景を持っています。こうした人たちにとって、きょうだい児保育への参加がそのまま社会への参加のきっかけにもなりうるのです。
4.きょうだい児保育の市域への拡大
4-1. 地域療育センターとともに柔軟なサポートを
3年間の市民協働提案事業を行った後、次なる目標はこの事業を継続することへ。そのためには、きょうだい児保育が横浜市の事業へ組み込まれることが必要不可欠です。ちょこレスは3年の間で、北部地域療育センターの利用者や職員から保育の意義やニーズについて聞き取り、結果をデータとして蓄積していきました。集めたデータをもとに、ちょこレスとのはらネットワーク、そして北部地域療育センターや都筑区こども家庭支援課などが再び協働し合い、関連部署に働きかけを行っていきました。
そしてついに、2024年度から横浜市の施設である地域療育センターの事業できょうだい児保育が実施されることに。合計4カ所の地域療育センターで、週5日間の保育が行えるまでに至ります。このときから北部地域療育センター内の保育は、のはらネットワークが単独で受託しています。
燕昇司さんは、「地域療育センターと私たちが事業の方向性を一緒に考えられるようになったことが、最も大きな変化です」といいます。地域療育センターの事業の一環としてきょうだい児保育が行われるため、保護者・障がい児・きょうだい児それぞれの状況を共有しつつ、地域療育センターとともに家族に対する総合的なサポートを実現できるようになりました。各家族に必要なサポートをタイムリーかつ柔軟に届けられるようになったことは大きな前進です。

「療育を安心して受けられるための方法を地域療育センターとNPOが一緒に考えられています。さらに事業の今後について障害児福祉保健課とも一緒に話し合えるまでに成長しました。本当に奇跡のような状況ですね」。燕昇司さんのこの言葉には、これまでの積み重ねに対する感慨が込められています。
4-2. 新しい仲間とより良い保育を実現する
事業化を機に、さくらんぼが西部地域療育センターでの保育事業の運営を担うようになります。実は、当初2回にわたり事業への参加を見送っていました。そうした状況の中でちょこレスの協議会へ出席した際に、「もし誰もきょうだい児を預からなければ、子どもはどのように過ごすのだろうか?」と強い危機感を感じた髙橋さん。きょうだい児保育の必要性に共感し、協力してくれる保育士の見通しが立ったため、本格的に事業に参入することを決意しました。
西部地域療育センターの「うさぎるーむ」は、もともと障がい児の保護者による自主的な運営からスタート。現在も当時のスタッフが継続して勤務しており、子どもや保護者に対する接し方のノウハウが自然と根づいています。そこに保育士が加わり、認可外保育施設の制度や規則と整合させながらより良い保育の実現に挑戦しています。

(画像提供:横浜市西部地域療育センター)
「面談のときに子どもを預けられるため、療育の先生としっかり話ができるようになった」など前向きな反応が保護者から多く寄せられていると、中西さんが嬉しそうに紹介してくれました。さらに中西さんは、「子育ての悩み事を保育士に気軽に相談できることも、保護者の心のゆとりにつながっています」と続けます。


髙橋さんと中西さんにはオンラインでご参加いただきました
2025年には、のはらネットワーク、さくらんぼ、さくらザウルス、さらに行政が参加した事業報告会が実施されました。そこでは防災訓練や地域療育センターとの連携、保護者への連絡方法など現場の課題を共有。3団体と行政が助け合う体制が少しずつ形づくられています。
5.きょうだい児が、健やかに生きられるために
良質な保育の時間を楽しむことは、きょうだい児本人にどのような変化をもたらすのでしょうか?燕昇司さんは、「大きな変化がたくさん起きます」と実感を込めて語ります。
療育に追われる家庭では、きょうだい児は「迷惑をかけないように」と感情を抑えることが少なくありません。そのため保育に初めて来たときのきょうだい児は、喜怒哀楽を一切見せないか、または聞き分けのいい子としてふるまうか、どちらかの傾向が強いそうです。乳児でも、自分がいまこの場所に預けられていることを理解しながら大人しくしている子がいるほどです。
そのため、きょうだい児保育では、子どもが自分の感情を表現できるまで丁寧に時間をかけて接し続けていきます。それを3カ月ほど継続すると、保護者と離れるときに泣き出す子が現れます。「遊ぶと楽しい」、「外の空気を吸うと気持ちがいい」、「お母さんと離れると寂しい」、自分の気持ちに気づき、少しずつ感情を表現できるようになるのです。保育士やサポーターは、このような感情の発露を見逃さないように目を配っています。

保護者にとっては、困りごとが増えたように思えるでしょう。しかし、燕昇司さんはそのときを「感情の表現が素直にできるようになった素晴らしい瞬間」と捉えています。その価値を保護者へ伝え、「一緒に困って、一緒に次の方法を考えていきましょう」と言葉をかけるそうです。保育の中でのこうした経験が、大人や社会を信頼しながら育つための土台となり、きょうだい児が孤立感を抱えたまま成長することを防ぎます。
6.おわりに──持続的なきょうだい児保育に向けて
横浜市の事業として実施に至っているものの、きょうだい児保育事業は永続的な予算の確保が確約されているわけではありません。そこで、行政、NPO、企業などが率直に話し合い、行政の予算だけに依存しない継続的なモデルを模索している最中です。
きょうだい児保育は対象となる子どもの数が限られており、大きな利益が出る事業にはなりにくいもの。そうであるからこそ、持続的な仕組みを考えるうえで、各方面の知識と新たな連携が必要です。「これからはソーシャル・ビジネスなど、接点のなかった異なる分野の方々ともつながることが求められます。私にはない知見を持つ人々と、上手な方法で連携していきたいです」と燕昇司さんは率直な心境を語ります。
自己表現を抑えがちなきょうだい児に対して、本人の気持ちや感情に寄り添う手厚い保育を実現したい。この変わらない思いを胸に、新たな協働の方向性を探っているのです。
最後に、きょうだい児保育について四者それぞれが抱く展望を共有いただきました。

木村さんは、「取組自体を知っていただく機会を増やしたいです。勉強会や講演会で、きょうだい児保育のお話ができたらと思っています。その中で、共感し合える人たちを探していきたいですね」と優しい笑顔を浮かべました。
「今後は療育を必要とする子どもが増えていくと思います。その中で、きょうだい児が持つ子どもとしての権利を守る仲間を地域の中に増やしていきたいです」と、髙橋さんからは熱い意気込みが示されました。
「事業継続のためには、人員と資金の両方の確保が必要です。これまでNPOとして培ってきた知識やつながりを生かしつつ、新しい支援の形を考えていきたいです」と語る中西さんの言葉からは、真摯な気持ちが伝わってきます。
そして、レポートの締めくくりに、燕昇司さんが掲げる目標を紹介します。
「この事業に関わる保育士は、『来年この仕事が存続するのか分からない』という不安定な状態の中で働いています。本来この取組は社会的に広く認知され、正当な評価が得られる活動だと思うんです。保育士が『私の専門は、きょうだい児の保育です』と胸を張っていってもらえるように、自分のできることを精一杯取り組んでいきます」
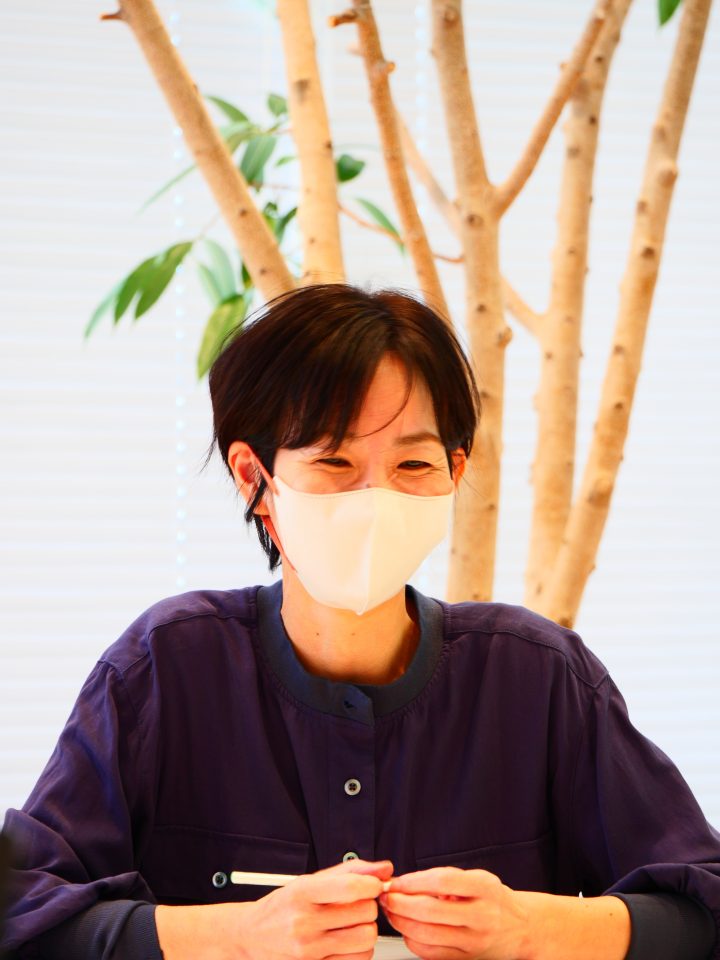
多様な主体の協働が、きょうだい児の保育の発展を支えてきました。困難な状況に置かれている子どもそして家族がより豊かに生きるために──地域全体がつながり、ともに力を合わせることで生まれる可能性と希望がこの取組にはあふれています。

※「横浜市北部地域療育センター」「横浜市西部地域療育センター」「横浜市中部地域療育センター」は、2回目以降の言及の際は施設名冒頭の「横浜市」を省略して記載

